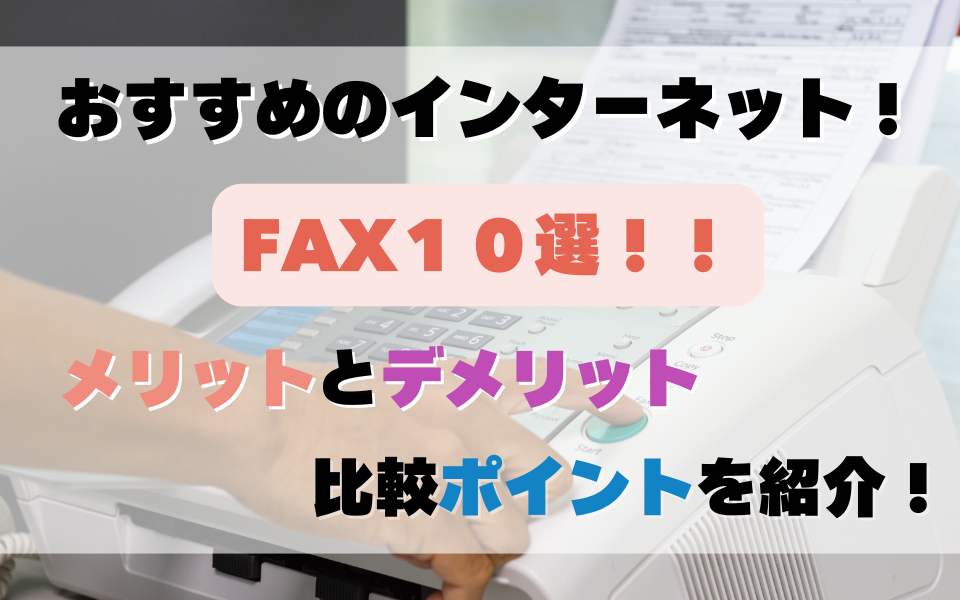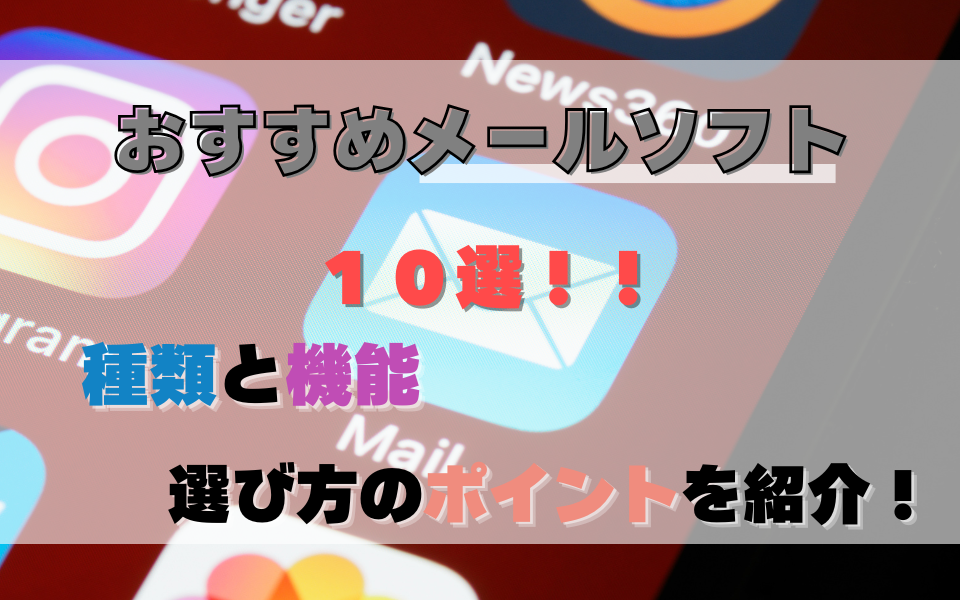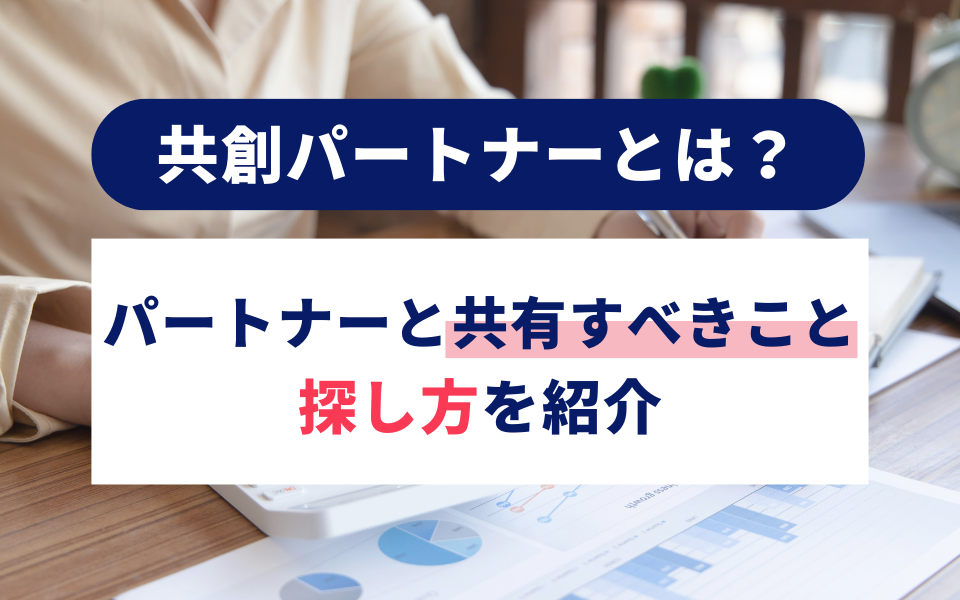
共創とは、企業とそのステークホルダーが協働し対話しながら新たな価値創造を行うことを指します。
共創パートナーはともに共創に取り組む企業のことを指します。
様々なサービスや物に溢れる現代では、自社の優位性や独自性を出すことがますます難しくなっています。時代の変化に伴い、日に日に変化するビジネス環境についていきながら、競争優位性を自社のみの取り組みで保つのは困難になりつつあるため、共創により新たな価値の提供を試みる企業が増えています。
これらの取り組みにおいては、競争のパートナーとしてどんな企業を選ぶのかが非常に重要になります。
この記事では、共創が求められる背景や競争により得られる期待効果、共創パートナーの探し方を紹介します。
共創パートナーとは

共創とは「多様なステークホルダーと協力しながら新しい価値を創造する」という概念のことを指します。異なる経験や専門知識を持つ人々が集まり協力して問題を解決することで、新しい製品やサービス、プロジェクト、イベントなどを開発することを目的としており、イノベーションのきっかけとしても注目されています。
「共創パートナー」とは、上記の共創プロジェクトにともに取り組むステークホルダーのことを指します。
共創のメリット

共創のメリットとして以下の3点を紹介します。
- 消費者の声を反映できる
- 新しいビジネスアイディアが生まれる
- リソースの補完
消費者の声を反映できる
共創には提携タイプや双方向タイプ、共有タイプなど様々な提携方法がありますが、消費者と協力しながら課題解決を進めていく双方向タイプの場合は、消費者の生の声を反映しながら共創を進めることができます。
消費者の生の声を聞く機会は貴重であり、新たな視点でアイディアを生み出す機会としても有効です。消費者の意見を実際の商品・サービス開発に生かすことができれば、市場での優位性を高めることも可能になります。
新しいビジネスアイディアが生まれる
自社のみでの事業開発ではこれまでの社内の慣習や取り組みの事例にとらわれて同じようなアイディアしか出てこない可能性があります。b。
リソースの補完
異なる領域での技術やリソースを持つ企業と共創することにより、自社のみのリソースでは実現することのできない事業において、他社からリソースを補完し、事業を進めることが可能になります。
高度な技術を持つ人材を自社内で一から育てるには時間もコストもかかるため、共創によりパートナー企業から補完できるとコストカットにもつながります。また、他社の技術に触れることで参加メンバーのスキルアップにもつながるでしょう。
共創のデメリット

共創のデメリットとして以下の3点を紹介します。
- 情報漏洩のリスク
- ルールの管理が煩雑になる
- 自社都合での解消が難しい
情報漏洩のリスク
共創ではそれぞれに事業が自社のノウハウや技術を公開し、生かしていくことでプロジェクトを推進していきます。そのため、共創相手に自社の重要な情報が漏洩するリスクがあります。
自社の技術やノウハウを守りつつ共創を実現するためにもNDAを締結するなど事前準備を徹底しておきましょう。
ルールの管理が煩雑になる
共創を進めていく上では両者の様々な権利の問題が絡みます。お互いが技術やリソースを提供しあい、生み出した利益はどう分配するのかなど、共創を実施する前に想定される事柄に関してはルールを決めておかなければ後々大きな問題に発展する可能性があります。
ルールの管理が煩雑にはなりますが、細かく決めておくことが重要です。
自社都合での解消が難しい
共創を進めていく中で、想定したものと違った、思ったより自社にメリットがなかったということがあっても多くのステークホルダーを巻き込んで進めていくプロジェクトにおいては自社の都合のみで関係を解消することが難しいです。
後々、想定と違ったということにならないように、事前のすり合わせを十分におこなっておく必要があります。
共創の実践に必要なこと

共創の実践には以下の3つの要素を共有することが必要だと言われています。それぞれについて紹介します。
- 価値の共有
- 体験の共有
- 技術の共有
価値の共有
価値の共有とは、社会のどんな課題を解決したいのか、ユーザーのどんなニーズに応えたいのかなどといった、共創を実践するためのそもそもの目的となる部分を互いに擦り合わせることを指します。
そもそもの共創の目的が互いに一致していなければ、プロジェクトを成功させることが¥は難しくなります。互いに同じ目標・目的に向かって自社の強みやリソースを出し合うことが成功につながります。互いに目標を確認し合い、納得した上で推進していくことが重要になります。
体験の共有
共創を進めていく中で、パートナーの事業や技術や強みなどを実際に体験することで、相手への理解と信頼感を深めることが大切です。
プロジェクトの立ち上げからアイデア出し、開発、ビジネスモデル構築、事業化準備など、共創の推進には様々な場面で壁にぶつかることも多くなります。事業化までの過程をパートナーと共有することで団結力が高まり、同じ目標に向かって進みやすくなります。
また、多くの体験を共有することで、互いの強み弱みを知ることができるため、進行中のプロジェクトに活かせるだけではなく、新たな共創プロジェクトのきっかけになる可能性もあります。
技術の共有
共創の大きな目的の一つに自社のリソースや技術では実現することのできないプロジェクトの不足部分を共創パートナーに補ってもらうことが挙げられます。
共創パートナーから自社にない技術を提供してもらい、一方でパートナーには自社の技術を提供することで、一から自社で技術を構築するよりもコストを抑えつつ、スピード感を持ってに業界の中で技術を補完しながらプロジェクトを進めていくことができます。
共創パートナーの探し方

共創を実施するには、ともに事業を作り上げる共創パートナーの存在が必須です。
ここでは、共創パートナーを見つけるための方法を3ステップに分けて紹介します。
- STEP1:パートナー候補のリストアップ
- STEP2:パートナー候補への連絡
- STEP3:共創による取り組みのディスカッション
STEP1:パートナー候補のリストアップ
まずは共創パートナーの候補となりうる企業をリストアップします。仮説を立て、その仮説に該当しそうな企業・団体をリストアップします。
ここでいう仮説とは共創プロジェクトにおける実現したい目標の細分化になります。仮説の内容としては以下のものが挙げられます。
- どの市場に対して何を提供するのか
- どんな課題を解決したいのか
- 提供したい価値や解決したい課題に対して、規制強化・緩和や政府の補助金など、実現を後押しするような情報はあるか
- 提供したい価値や解決したい課題に対して、自社では何ができそうか、強みを活かせるか
- 提供したい価値や解決したい課題に対して、自社に足りないものは何か
また、共創パートナーを選ぶ際には、共創の目的に強く関連する評価軸を設定することが成功のためのポイントとなります。共通の評価軸の内容としては以下のものが挙げられます。
- 自社が想定している共創プロジェクトのコンセプトとの親和性が高いか
- 他社との連携を積極的に行っている実績があるか
- 自社にはない顧客層との接点を持っている企業であるか
- 想定している顧客の規模感が自社と合うか
STEP2:パートナー候補への連絡
パートナー候補の絞り込みができたら、実際にパートナー候補に連絡をとり、ディスカッションの場を設定します。
ディスカッションの場へと繋げるために、パートナー候補に連絡をとる際にはディスカッション資料を作成し、相手企業にも共創相手として魅力的であるということを伝えなければなりません。
作り込みすぎる必要はないため、共創を行うことでパートナー候補企業にとってもメリットがあること、どんな共創の可能性があるのか、中長期的にはどんなプランを考えているのかなどを議論のテーマとして持っていくことが重要です。
パートナー候補への連絡方法としては、これまでのネットワークを活用する方法や、ビジネスマッチングサービスなどのパートナー紹介サービスを利用する方法が考えられます。
STEP3:共創による取り組みのディスカッション
パートナー候補との初回のディスカッションである程度共創パートナー候補が見えてきたら、2週間〜1カ月以内など初回からあまり期間が開かないうちに2回目のディスカッションの機会を設定しましょう。
共創におけるプロジェクトの構想を具体的にするためには複数回のディスカッションが必要になります。取り組みの構想案を早く短期的な行動指針に落とし込み、双方合意して共創のスタートを切ることが重要になります。
また、構想がある程度固まってきた段階で、短期的な施策を素早く実行に移すためにも社内調整を早めに行うことが重要です。特に大きな組織の場合、共創のプロジェクト立案を進める部署と実際に推進する部署は異なることが多いため、事前に社内部署を巻き込み、目的を共有しておくことが重要です。
共創パートナーをお探しならレスターマッチングサービスがおすすめ
共創は、企業が様々なステークホルダーと協業し、新しい視点やアイディア、技術を取り入れることにより新たなイノベーションを創出する際に有効な手段です。
共創を行うためには、自社の強みを活かし、プロジェクトの目標に賛同してくれる共創パートナーを見つけることが重要ですが、自社のみで相手を探すのは大変です。事前の準備や相手へのコンタクトなどパートナーとなるまでには様々なプロセスを踏んでいく必要があります。
「共創パートナーを探したいが何をすれば良いかわからない」、「共創パートナー探しをともに行ってほしい」という場合には、レスターマッチングサービスがおすすめです。
『レスターマッチングサービス』は、コンサルティング型のビジネスマッチングサービスで、担当者が企業の課題をヒアリングし最適な企業候補の選定から解決策の提案まで行います。
独自のネットワークに加え、他のビジネスマッチングサービスのデータベースや金融機関との連携により幅広い企業を紹介することが可能なため、共創にともに取り組む企業探しをお手伝いすることが可能です。