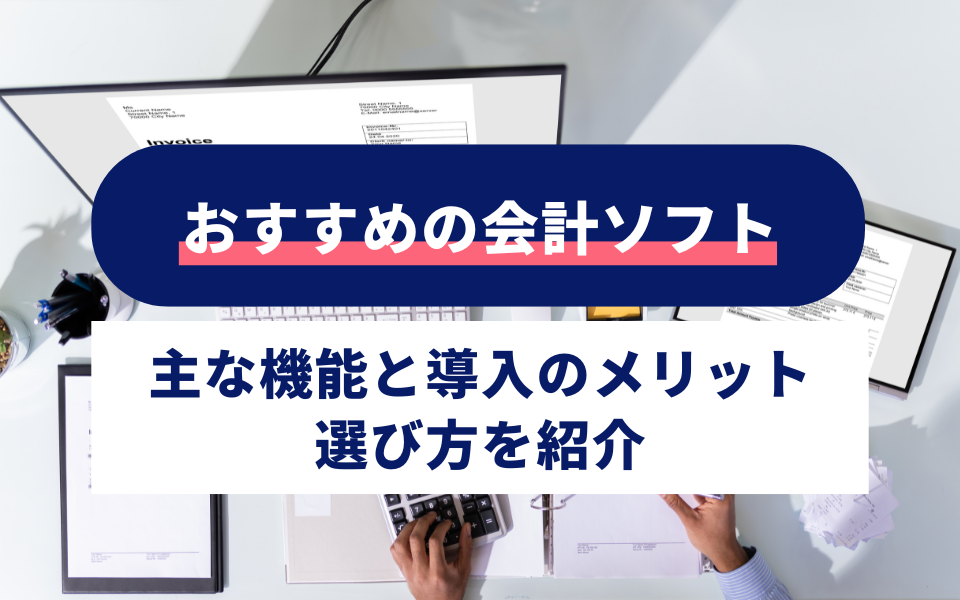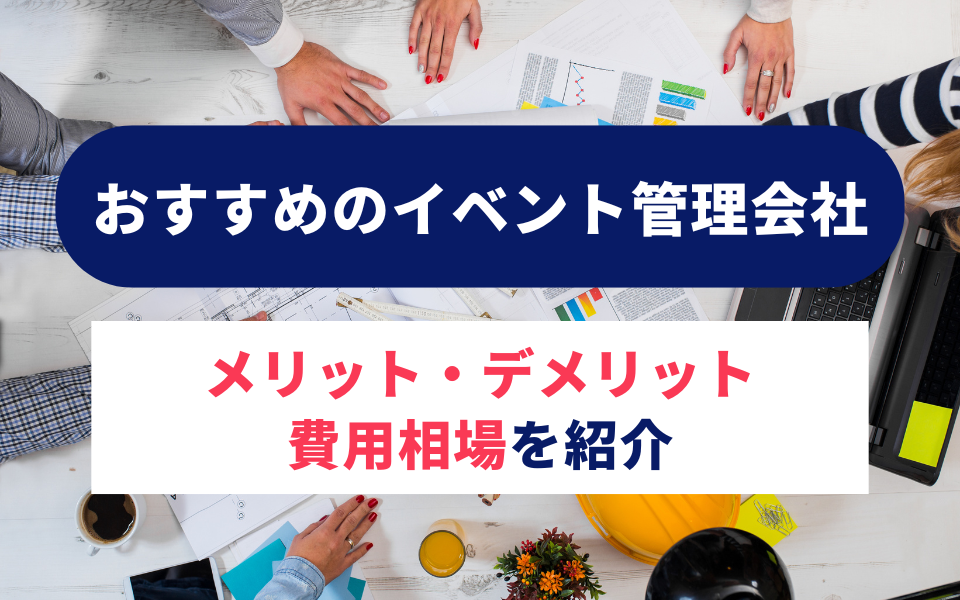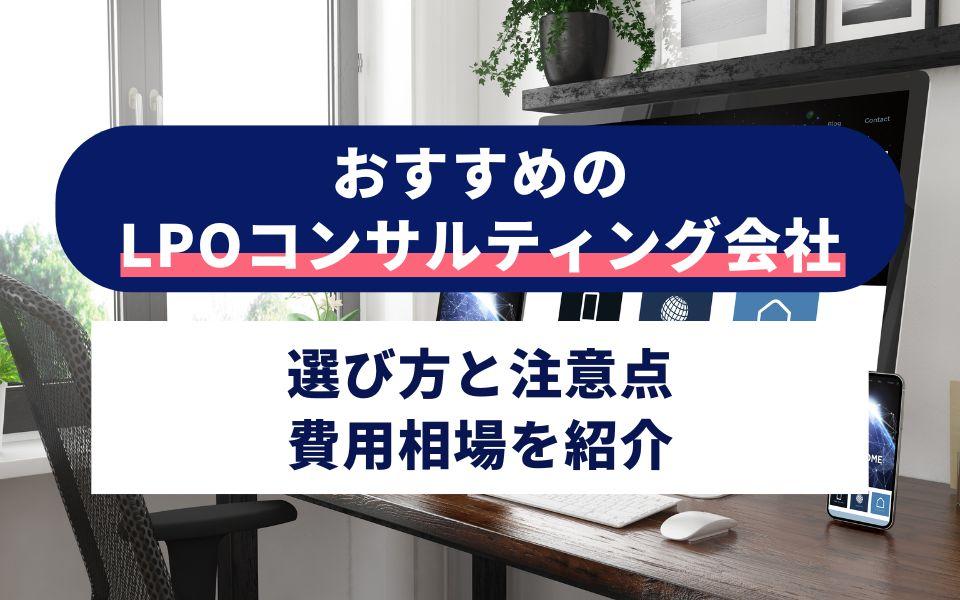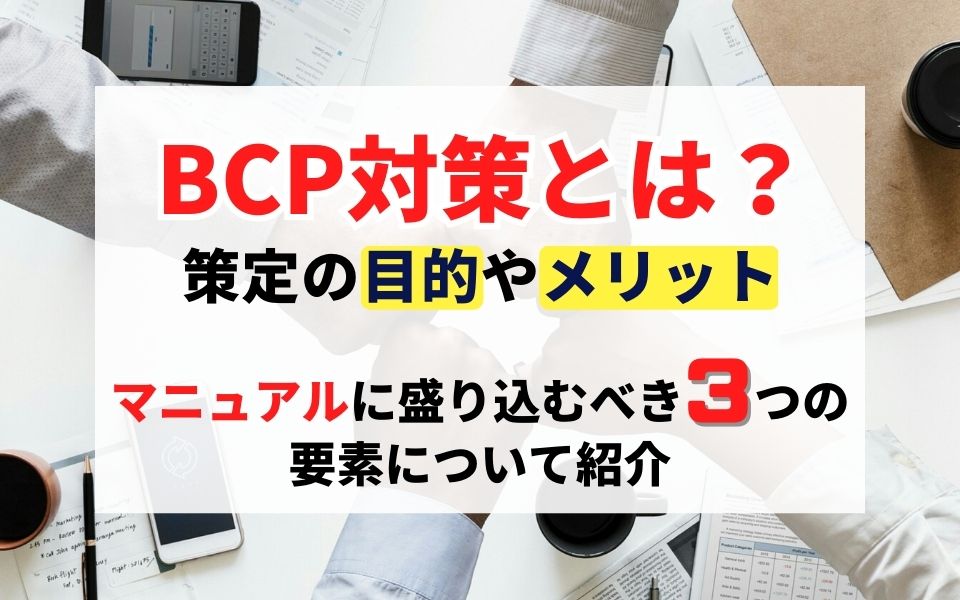
近年、増加している地震や台風などの自然災害に加えて、コロナなどのパンデミックも起きたことから、企業のBCP対策の重要性が高まっています。
また、企業はこのような地震や火災などの自然災害だけではなく、社員の不祥事や事件・事故などの人的災害によるリスクにもさらされています。
実際にBCP対策を行う上での、目的や策定のメリット、マニュアルに盛り込むべき3つの要素についてお伝えします。
BCP対策とは

BCPとは事業継続計画のことで、自然災害やテロなどの緊急事態が発生した際に、企業の事業への損害を最小限に抑え、早期復旧を目指す計画のことです。
会社を守り経営を続けていくためには、台風や火災、地震などの自然災害のみならず、不祥事や事件・事故などの人的被害に合った場合に、企業の中核事業をいち早く回復させ継続していくことが求められます。
その際の対応や復旧手順をまとめたものが事業継続計画です。
BCP対策が必要な理由

近年、重要性が高まっているBCP対策ですが、なぜ必要なのでしょうか。
BCP対策は、自然災害や人的災害などの有事に会社や従業員を守るために必要とされています。
世界的には2001年にアメリカで発生した同時多発テロをきっかけに注目されました。ニューヨークの世界貿易センター付近にあった多くの企業が、事前に行っていたBCP対策のおかげで業務への影響を最小限に抑え、早期に事業を復旧させたことで注目が集まりました。
日本では2011年の東日本大震災をきっかけに、地震などの自然災害により大きな被害を受けた際の経営や事業、人材に対する対策が不十分であるという認識が広がったことで注目され始めました。
地震やテロだけではなく、近年では新型コロナウイルス感染症の拡大によりリモートワークが推進され、生産性にも影響を及ぼしました。
企業の経営や事業の存続をおびやかす外的要因・内的要因などが多いこの時代には、事業継続のためのマニュアルを策定し事前に十分な対策をとっておくことが非常に重要です。
BCP対策を実施するメリット

BCP対策をしておくメリットは、有事の際に事業の早期復旧が見込めるだけではありません。
ここでは、BCP対策を行うメリットについて紹介します。
- 企業の信頼性を高める
- 緊急時に強い会社になることで競争力が高まる
- 自社の強み弱みを把握し、経営戦略に生かすことができる
企業の価値や信頼性を高める
企業がBCP対策を行うことで、社会からの信頼を高めることができます。
BCP対策の実施は自然災害や人的災害といった不測の事態への備えにつながるため、もし実際にそのようなことが起こったとしても対応できる力がある会社と評価されます。
災害などが発生した際に、早期復旧し事業を継続できる見込みがあり、緊急事態による倒産・事業継続困難の可能性が低いと考えられるため、取引しても安心な企業という認知を得ることができます。
緊急時に強い会社になることで競争力が高まる
緊急時からの回復の速さは競争力を高めることにもつながります。
BCP対策を実施することで、緊急時に被害を最小限に抑え、いち早く事業継続を開始することができます。他の企業よりも早く事業を再開できれば、他社がまだ業務を開始できていない段階に業務を進められるため、その分優位性の高さにつながります。
自社の強み弱みを把握し、経営戦略に生かすことができる
BCP対策を策定していく段階では、災害時に何を最優先で復旧させなければいけないのか、一番重要なコアとなる事業は何なのかを把握していく必要があります。
これらの段階を経ることで自社の強みや弱みを把握することができるため、今後の経営計画に活かすことも可能になります。
BCPマニュアルで策定すべき3つの項目
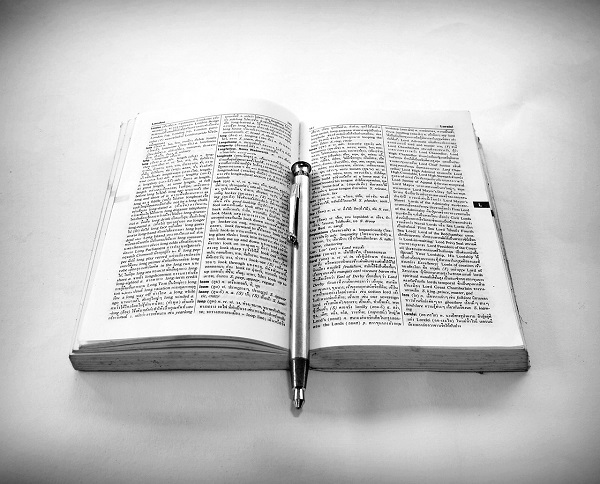
BCP対策の一環としてマニュアルを策定する際、どんな項目についてのマニュアルを策定すればいいのでしょうか。対策すべき項目は地震や火災、台風などの自然災害に対する項目だけではありません。
ここでは、BCPマニュアルを作成する際に必要な3つの項目について紹介します。
- 自然災害に対する対策方針
- 外的要因に対する対策方針
- 内的要因に対する対策方針
自然災害に対する対策方針
災害大国の日本では、発生する可能性が高いため最も重要な対策項目になります。
自然災害に該当するものとしては以下の可能性が考えられます。
- 地震
- 台風
- 津波
- 洪水
- 大雨
- 豪雪
- 竜巻
- 火山噴火
- 高潮
自然災害の場合には被害が広域に及ぶことが考えられます。人命救助への対策からオフィスが使用できなくなった場合の対策、システムや物流が機能しない場合の対策など、広範囲に渡って考慮する必要があります。
対策項目としては以下の内容が挙げられます。
- 人命救急の方法
- 避難方法
- 安否確認方法
- 被害状況の確認方法
- 通信手段の確保
- 物流の確保
- 代替オフィスの確保
- 停止した事業を復旧させるための代替案
- 緊急時の連絡先リストと優先順位
地震や台風などの自然災害によって被害が発生した場合、社員の安否確認を含め被害状況を確認するために連絡手段の確保は非常に重要になります。通信手段の確保は内部コミュニケーションの他にも取引先や行政との外部コミュニケーションを確保するという観点に置いても重要度が高いと考えられます。
また、本社などのワークエリアが使用できなくなった際に本部として機能する場所を確保しておくことも重要です。
物流は、業務関連の必要物資だけではなく、災害時の生活物資を確保するためや、業務再開後の仕入れ・納品に必要な最低限の手段を確保しておく必要があります。
外的要因に対する対策方針
外的要因による事業へのリスクとして考えられる項目には、取引先の倒産、通信障害、サイバー攻撃などがあります。また、近年では新型コロナウイルス感染症の拡大によって、感染症に対する対策の必要性も出てきました。
特に、取引先の倒産は、倒産先との取引金額や重要事業への貢献度などにもよりますが、自社ではコントロールすることが難しいため、事前にできるだけの対策をしておく必要があります。
取引先を複数持つようにするなど、適切なリスクヘッジが求められます。
- 脆弱性対策
- 仕入先の変更先リスト
- データの復旧方法
- データ漏えいの際の顧客への通知方法
- 取引先への連絡リストと優先順位
内的要因に対する対策方針
内的要因としては、セキュリティインシデントや社員の不祥事や人的ミスなどが挙げられます。
こちらは外的要因に関わる部分でもありますが、インターネットの発達とともに、ソフトウェアの脆弱性を悪用した不正アクセスやコンピュータウイルスへの感染、個人情報漏洩や情報改ざんなど、セキュリティ面でのインシデントが多発しています。
こうした状況が発生すると、企業の取引先や市民からの社会的信用が下がる原因となってしまい、経営にも大きな影響を及ぼします。
これらの事態が起こってしまった際に、迅速に対応し、被害を最小限に抑えるためにも、外的要因に対するBCP対策の項目として以下のような内容を策定しておく必要があります。
- 社員へのセキュリティ教育
- 社外への謝罪文のテンプレート
- 問い合わせ窓口の設置
- 再発防止策の策定
- 記者会見開催の手順
- 取引先の連絡リストと優先順位
BCP対策の運用で重要なポイント

BCP対策は、マニュアルを策定して終わりではありません。緊急時にしっかりと機能してこそ意味があるため、いかにうまく運用できるかがポイントになります。
最後に、BCP対策を運用していく上で重要なポイントについて紹介します。
- 最初から完璧を目指さない
- 策定後のテスト・改善を継続して行う
最初から完璧を目指さない
BCP策定では、最初から完璧な完成度を目指さないことがポイントです。
自然災害や人的災害はいつ起こるかわからないため、できるだけ早くBCP対策マニュアルを完成させることが先決です。社会状況が複雑化し、日々様々なリスクに晒されている企業にとって、起こりうる全てのリスクに対しての解決策を網羅した計画を立てることは不可能です。作成を試みても、いざという時にマニュアルがなくては何も意味がありません。
策定時の調査などでわかった自社で守るべき優先度の高い事業などに合わせて、優先度の高い項目から作成していくことが必要です。
策定後のテスト・改善を継続して行う
マニュアルを一通り作成することができたら、テスト・運用を通してより実用的な内容へと完成度を高めていくフェーズに入ります。
テスト・運用を通してマニュアルの内容を充実させ、社内での訓練などを通して実際にマニュアル通りに動けるのかを確認することも重要です。
できるのであれば、社内だけの運用・訓練だけではなく、広域災害に備えて地域の関係拠点やサプライチェーン企業など社外のステークホルダーを含めて検討・訓練できるといいでしょう。
運用や訓練をしていく中で発見された改善点をフィードバックしたり社内で共有することによってBCPマニュアルの実効性を高めると同時に、組織全体で緊急時に対する意識を高めていくことが重要です。
BCPをより具体的で実践しやすいものにするために、災害が発生したときにどのような流れで事業を平常状態に戻すかをイメージしておきましょう。
まとめ:BCP対策に取り組むならレスターマッチングサービスがおすすめ
BCP対策は、企業を自然災害や人的災害のリスクから守り、該当時には被害を最小限に抑え早急に復旧するために必要とされています。
様々な災害やリスクが多い現代では、より重要度が高まっているBCP対策ですが、自社で策定しようとしても手順や内容がよくわからないという場合もあるのではないでしょうか。
その場合に、レスターマッチングサービスがおすすめです。
レスターマッチングサービスは、技術や商品を「買いたい」企業と「売りたい」企業をマッチングするサービスです。
解決したい課題を掲載することで、課題解決につながる取引先をパートナー企業として選定できます。